解像度を上げる
最近ちょっとチャンスがあり、とあるグループのレポートを
まとめて読む機会がありました。その傾向が面白かったのです。
それは、最近の新人や若者(Z世代)に対して、我々はどのように
指導していったらいいか。という論調でした。
そこで感じたのが、書かれていたZ世代の特徴と日頃感じている
ことに大きな乖離があるということ。なので、それは違うよな。
という気持ちだったのですが、ちょっと待てよ。
違う原因は解像度の違いだったのです。
Z世代とくくることはできても、
その一人ひとりを括ってしまうと無個性の集団になってしまう。
つまり個人と集団を比較した時の違和感だったのですね。
実はこれ、多くの場面でギャップを生む原因になっているのです。
語っている解像度が違うから話が噛み合わないし、良い解決策が
見つからない。しかもほとんど無意識でやっている。
ということで、「泣いた赤鬼」という物語を思い出しました。
人間と鬼、善と悪の対立から、鬼の解像度をほんの少しだけ上げる
(赤鬼と青鬼)だけで、見え方が全く変わってくる。
そんな感じで考えるとなんかよくないですか。
【今週の1冊】
「私の美の世界」
1968年 森茉莉 著 新潮文庫
森鴎外の娘である森茉莉エッセイ。
連載物をまとめた本は、一気に読んではいけない。
読まない方がいい。
週刊誌のエッセイなのか、月刊誌のエッセイなのかに
合わせてその間隔で読む。書かれた時代に関係なく。
多分作者の思考に近いと思うから。
AIは単なるツール
AIでなくなる仕事が一気に増える。新人がやることが無くなる。
AIを使っていないと時代遅れになる。
今日この頃。いかがお過ごしですか。
そんな私も仕事でAIは活用しているけれど、単なるツール。
もっと違う使い方や高度な使い方があるのかもしれないので、
的外れなことを書いている危険性もあるのだけれど。
新しいものに拒否感はないし、積極的に使っていく派だけど、
だって人間だもの。総体的な五感+
AIは追いつかないし、違う土俵にあるんですよね。
少し前の3Dテレビや、VRやARが流行らないのも人間の感覚が
受け入れないからなのです。だって気持ち悪くなるんだもの。
今、
あそこに書かれている文章を読むと気持ち悪くなるのです。
たまに読んでみても、そうだけどそうじゃない感。これから
どんどん進化すると違和感は解消するのかもしれないけれど、
それはそれで、まだまだ便利なツールでしかない。
AI便利です。とても便利。使わない手はないけれど、
教育や学習、研修の領域も全く同じで、
それぞれの特性を活かして使い分けることが大事。
ちなみに打合せのほとんどはオンラインのままで、
の後で勝手にAIで要約してくれるのは、
ということで、しばらくは有望なツール(相棒)
【今週の1冊】
「海辺のカフカ」
2002年 村上春樹 著 新潮社
カフカからかな。村上春樹の新刊は発売当日に買って
その日から読み始まるようになったのは。その日のうちに
読み終えるのがもったいなくて、最後はあえてゆっくり
ゆっくり読む。カフカは出張に持って行って出張先で
読んでいたことをその時に景色とセットでよく覚えています。
いい風が吹いていました。
そのカフカも3回目。物語はわかっているはずなのに
その度に新鮮な気持ちになるのは、こちらの読み方が
変わってきているからなんでしょうね。
スマホが登場しない以外は、23年前と今は何も変わっていない。
人も気持ちだけでなく、社会のこと、その他たくさん。
人間って少しづつ、
それでも着実に。
久しぶりの村上春樹。やっぱり好きだなあ。
間違いを修正する力
ちょっとした失敗ばっかりですよね。生きてると。
白い服を着ているから慎重に麺を食べてたのに、
最後の一口が飛び跳ねたり、言わなくていいことなのに
ちょっと口が滑っちゃったり。口は災いの元?
そんなことがあっても大丈夫!
忘れることができるから。
ということで、もっともっと思ったことや感じたことを
自由に言っていこうよ。
思うのです。だって面白いんだもの。思いっきり笑えるし、
誰も傷づかない。いや、ちょっと傷つくかもしれないけど、
それこそかすり傷だしすぐ治るし、お互い様。
人間の大きな魅力、能力、特徴は間違いを修正する力があること
なのに、間違いを犯さないようにしようとすると、どんどん
面白く無くなってくるよね。と堀辰雄を読みながら感じて
しまいました。さ、バカ殿見て大笑いしよ。
【今週の1冊】
「風立ちぬ」
1936年 堀辰雄 著
名作と言われてまだ読んでいなかったのでちょっと読んでみました
1904年生まれの堀辰雄。1904年は日露戦争の年。
それから第一次世界大戦に向かう中での少年、青年期を迎えての
風立ちぬ。
今ならもっともっと自分を他者を深く扱っていいんだよ。
変わったのは時代の空気なのかそれとも
時代の変わり目。そんな感じがする今日この頃ですね。
政治も経済も社会もこれから数年で大きく変わるでしょうね。
変化の中に生きている。情報化社会。加速度的な変化の時代、
我々は何をしたらいいのか。
実際はそんなことはなく。いつの時代も大きく変化をしている。
違うのは視点。変化が大きいと感じている時は、目の前のことに
関心が向いている時。
遠くから見るといつも海は穏やか。近付いていくと波があり、
時には大しけ。
視点を離していき、時間軸を伸ばしていくと穏やかで、
変化しているだけ。
なので変わったのは時代の空気ではなく、自分自身。
自然の大きなゆっくりした変化に比べると自分自身の変化は
とても大きい。間違いなく年をとっていくし、自分を取り巻く環境
は変わっている。
ということで、時代の変化が大きいと感じた時は、一度落ち着いて
自分が変わったということを冷静に見る余裕が必要かなと。
【今週の1冊】
「化物語」
2006年 西尾維新 著 講談社BOX
西尾維新はこれまでに何冊か読んでいますが、
今年のGW、所沢の角川武蔵野ミュージアムに行った時に
「マンガ・ラノベ図書館」
街中の公共の図書館とは年齢層も本の読み方も全く違って
ちょっとしたカルチャーショックを受けたのです。
中高生が多くて、
ラノベって何冊か読んだことはあって(西尾維新も)それでも
いわゆる小説ではなくて、
大いなる勘違い。全く違うジャンルだけどきちんと小説だし、
とても面白いのです。ただなんというかノリが違うというか、
その文体があるのかセオリーがあるのか、
入り込めない。それは海外のSFも時代小説も同じ。
頭のスイッチを切り替えて違うモードにすればとても楽しめる。
これはこれでありだなあ。日本の文学の新しい可能性があるなと
今更ながら気づいてしまいました。
先日の芥川賞、直木賞は受賞作なしと発表されましたが、
結構ハズレが多い芥川賞よりラノベの方がずっと楽しめますね。
ゆるりと
暑い日が続きますね。
ふと、窓の外を眺めると白い雲、青い空、濃い緑の葉っぱ。
窓を開けると蝉の声。夏!いい感じです。
来週の本で取り上げる予定ですが、
「人間には12の感覚がある」を読むと、色や音、
それを総合して感じることで、
ということで、体全体で季節を感じるのは、
良い感じですよね。
その感覚ってその名の通り、感覚、感じ方なので人それぞれ。
一人ひとり違うから言葉にしても全く同じように伝わらないし、
理解できない。なので、まあいろいろとゆるりといきましょう。
仕事を効率化して時間が生まれたら、その時間を新しい仕事で
埋めるのではなく、余裕やゆとりの時間にしませんか。と
以前書きましたが、あえて何もしない時間をつくってみる。
そんな夏にしませんか。だって暑いんだもの。
【今週の1冊】
「ボヴァリー夫人」
初版 1856年 フローベール 著
じっくりじっくり時間をかけて読みました。
他の本を並行して読みながら1ヶ月かけて。
やっぱり、
読みながら、トルストイのアンナカレーニナ(1873)や
モーパッサンの女の一生(1883年)と比べながら、この時代に
思いを馳せて。
第一世界大戦前で、第二次産業革命後の平和で社会的な価値観が
変わる時期。面白い小説って平和な時期に書かれるんですよね。
人の自由な生き方や内面を描くことができるから。
解説によるとアンナが読んでいた本がこの「ボヴァリー夫人」
お互いに影響を受けて深め合っていたことを想像するのも面白い。
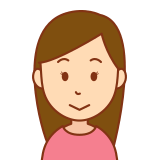
この1年、挿入画像のテーマを「飲み物」にしてました。次の1年は変えますよ~。何にしようかな~



コメント